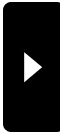2010年07月21日
部門別管理

こんにちは。
鏡でございますm(__)m
あついです(>_<)
今日も熊本は・・・
今日は、「部門別管理」について。
いくつかの拠点やいくつかの事業をなさっておられる企業で、損益計算書は「部門別」に管理されていますでしょうか。
たまに見かけるんです。
何もかもを一緒にして損益管理をなさっておられる場合を・・・。
これじゃ、どこに原因があって、どうやってその対策を打つのかが全くわかりません。
年に一回、税理士さんへ申告をお願いしていて、そのために帳簿を作成している企業なんか一体どうやって会社を維持していかれるのだろうと思います。
別途毎月の試算表をきちんと作成し、自分たちで数字を読み取って検証・行動をされていれば別ですが、この厳しい世の中、市場が縮小し、客単価が下がり、前年度維持すらままならない時に、帳簿に無関心では、どんなに頑張っても『検証』がなされないわけですから、いろんな取りこぼしが出てくると思います。
もったいないです。
申告には部門別管理が必要ありません。会社全体の損益がきちんと表示されればいいので(正しく税金計算ができればいいので)、経営管理のための財務資料として利用するためには、「部門別管理」や「勘定科目」の設定の仕方がポイントになってきます。
顧問をお願いしている先生が、税金申告にウエイトを置いている先生であれば、自分たちの手間が増えないよう、試算表を経営管理に役立つ財務資料にはわざわざしようとしません。
なんとかして、顧客へのサポートをしてあげたいと思っておられる先生は、試算表の作り方、科目の設定の仕方が違います。
どうですか?どんなご指導を受けておられますか?
部門別管理のメリットは、事業ごと、拠点ごとの採算度を見れることです。
全体での管理では、どの部分が利益が低いのか、どこで赤字になっているのかが明確に出てきません。
また、飲食店の多店舗展開など、「事務所」部門を設定し、各営業部門へ「事務所」の経費を負担させていきますが、管理部門である「事務所」部門のコスト管理が常に必要になってきます。
また、部門別管理では、各営業拠点ごと(事業ごと)のコスト管理にも役だってきます。
不採算部門の存在を明確にするため、またその不採算の規模を明確にするためには、部門別管理は必須になります。
どんなに頑張っても、どうして利益が出ないのだろうか、どうしてお金が足らないのだろうか、という場合、ひょっとしたら、その解決のヒントが部門別管理の中にあるかもしれません。
是非、事業展開をなさっておられる企業は、税理士さんとも相談して、経営に役立つ財務資料の作成に力を入れていただきたいと思います。
そして、リアルタイムにその資料を活用し、スピード感を持って対策を打っていただきたいです。
決算書も試算表も、単なる“納税と借入のために必要な書類”にしてしまっていませんか?
これは、ひとつの『機会損失』ですよ。
数値は嘘をつきません。
もっと数値を活用した、また地に足のついた対策が打てるよう是非『財務資料』に一目置いていただきたいと思います。
2010年06月15日
『事業計画書』

こんばんは。
鏡でございますm(__)m
事業計画をここんとこガンガン作ってます(^_^;)
で、大体、
A予算:100%
B予算:80%
C予算:70%
の売上見込みだった場合に、それぞれ、B/SとP/LとC/Fがどうなるかをシュミレーションするんですが、大体、銀行さんは、100%のA予算はほとんど信じてくれないと思ってください。
70%達成したとき、つまりC予算で返済・納税ができるかどうか、その後のキャッシュフローはどうなるか、プラスになっているかがポイントです。
また、たとえ、70%達成の時でも、そもそもの売上根拠がどうか。
現実的な根拠だてとなっているかがポイントです。
単純な数字遊びではないことを証明しなくてはならないのです。
そこで、いろんな分析や根拠資料が必要となってきます。
キーワードは
「客観性」
です。
つまり、「第三者的視点」です。
数値面、プラン面が客観的に見てどうか、作成後も見直してやっています。
また、いろんな質問も想定しておいて、それに対する答えの資料も用意しておかなくてはなりません。
こういう資料作りも結構大変なんですが、
70%で計画を見られるというのも、結構キツイものですよね(^_^;)
70%の計画で、まずもってP/Lがプラスかどうか。
当然、利益が少なくなるわけですから、稼ぐキャッシュも少なくなります。
減価償却費が多いとまだいいのですが、設備等の固定資産も償却しつくしていたりすると、納税した後のキャッシュ(この場合は償却費がほとんどないと仮定したとき、「利益+減価償却費ゼロ=キャッシュ」とみれるので)が残らず、返済金が捻出できません。
当期のキャッシュフローはマイナス。
前期繰越分より、このマイナス分を補填し、繰越キャッシュフローはその分減少します。
中期計画の場合、2年目はその減少したキャッシュからスタートします。
2年目、3年目、4年目、5年目も全て当初計画の70%達成で計画した場合、5年通して、キャッシュも損益もプラスになることができるか・・・・。
経費は基本的に多めに設定してます。
勿論、突発的事項に対しての準備として、「予備費」は必ず設定します。
これは、つまり「遊び」部分ですね。
もしも、70%で損益もキャッシュもプラスにならなければ・・・・。
経費見直しなどが必要になってくるでしょう。
月々の返済額の見直しが必要になってくるかもしれません。
事業計画は、何も社内外に見せるためだけのものではありません。
本当に、現実的に自社がやっていけるかを想定し、その場合の対応策を準備しておくためのものでもあります。
よく、銀行借入をするから作ってほしいと頼まれますが、きっかけは銀行融資でも、せっかくの事業計画です。事業コンセプトから、理念、ビジョンなど、根本的な部分をお聞きして作成しております。
そういう事業の根幹部分のことをブレないように、定期的に確認・見直しをされている中小企業は多くはないと思います。
また、経営者の頭の中にあるのは、「漠然としたもの」です。
これは、当社が使用している「下書き用の事業計画書」を業種業態に応じ、選んで記入してもらうのですが、この時が良くそれがわかります。
それは、「書いてある言葉がほとんど抽象的な表現になっている」時です。
言葉が抽象的⇒具体的でない⇒課題が見えてこない⇒やることがわからない⇒行動につながらない
となります。
また、「いつ、誰に、何を、いくらで、どのようにして売りたいのか」がわかりにくくて、他社との優位性も曖昧だったりしています。
頭で考えていることを、紙に書き出すことで、今の自分の思考の完成度を確かめることができます。
これが思ったほど、ペンが進まないものです・・・(^_^;)
でも、書いていただいてます。
なんとか頑張って書かれた後は、抽象的な言葉が多い部分もありますが、社長さんの中で何かがちょっと変化したように思うときがあります。
「こういうところまで、正直今までじっくり考えたことがなかった」とおっしゃいます。
きっと、何か見えてきたものがあったのだと思います。
事業計画作成を通じ、あまり数字が得意ではなかった経営者さんも、少し数字と触れあうことで、大きな捉え方でポイントを押さえていただいているようです。
グラフ形式で見ていただくのも視覚に訴えるので非常に分かりやすいようです。
明日も朝一で事業計画つくりです。
明日は、社長さんの「夢」に向けての事業計画書策定です。
いいですね。
こういうのも。
なんか、わくわくしてきます。
社長さんの夢の実現へ向けて私も頑張りたいと思います!
2010年04月15日
借金はいつなくなる?

こんにちは。
鏡でございますm(__)m
さて、今日は、「借金をいつまで払うか」ということについて・・・。
稼いだ利益で借金を支払いますよね。
通常は・・・。
では、この通常の場合で、いつまで払っていくのか?
つまり、何年で借金がなくなるか?
ということをシュミレーションしてみようと思います。
このことを『借入返済年数』といいます。
では、
短期借入金 10,000千円
長期借入金 78,000千円
設備投資手形 0円
社債 0円 ※借入金等 88,000千円
当期経常利益 18,000千円
当期減価償却費 3,000千円
という会社があるとします。
この会社の場合の『借入返済年数』はどうなるでしょうか?
借入金等88,000千円÷{(経常利益18,000千円+減価償却費3,000千円)÷2(法人税率を利益の半分、50%とすると)}
=88,000÷10,500(←返済利益)
=8.38年
↑これ、実際の返済年数(融資契約上の年数)と比べてどうですか?
もし、実際の(契約上の)返済年数があと5年だとします。
しかし、この返済利益では、短期も長期も合わせて全部返済してしまう(無借金になる)なるには、5年ではなれないということです。
しかも、毎年10,500千円の返済利益が確保されて、それでも8.38年かかるということになります。
つまり、約定通りの返済ができていないことを表します。
ということは、不足した返済利益を補うために、また借入をしているということになります。
だから、残が減らない。
いつまでも返済が続く。
と、いうことになります。
これを計算して、10年以内の年数にとどまるようにすることというのが理想ですが、中小企業の場合は、おそらく厳しいので15年以内の年数にとどめていかないと、よほどの業績アップが見込めない限り借金漬けの生活から抜けれなくなるとみられています。
いかがですか?
対策は二つ!!
①返済利益を増やすこと
②借入残高を減らすこと(増やさないこと)
①は要は、『利益』を増やすしかない!ということです。
売上ではないですよ。
『利益』ですよ。
売上が減っても利益が増えればいいのです。
また、売上を拡大して、利益をさらに増やすことができればいいのです。
②は、不動産の売却、投資資産(株・預金等)の売却や解約などで得た資金で、一括返済をしたり、元金の内入れをして、借入金の残高そのものを減らすということです。
※しかし、これらの方法は切り札を使用することになるので、その後、いざという時のための切り札がそれだけ減ってしまう(なくなってしまう)ことになるということは忘れないでくださいね(^_^;)
①と②、どっちが簡単でしょうか・・・。
いや、どちらともそう簡単ではありませんが(^_^;)
実際に自社の年数を計算してみてください。
※見たくないものですが・・・(>_<)・・・是非!!
10年以上の場合、借金依存度が高くなってきていると思ってください。
考えたくないことですが、つらいことですが、まずは、経営者として自分の目で『事実』を確認・認識しないと現状からの脱却はありえません。
是非やってみてください。
2010年04月12日
オススメ!!

おはようございます。
鏡でございますm(__)m
皆さんの会社では、帳簿付けはどうされていますか?
また、給与計算はどうされていますか?
更に、売上の管理、在庫管理はどうされていますか?
今日は、オススメの事務系ソフトをご紹介します。
当社は、業界No1の勘定奉行のOBC(㈱オービックビジネスコンサルタント)の販売代理店をしておりますが、当社で取り扱っているこのソフトは、はっきり言って“高いです!!”
中小企業には、高い!!と思います。
で、ほとんどオススメしておりません。
でも、高いのには理由があります。
それは、使い勝手です!!
私もこれまで様々な会計ソフトを使用してきました。
(これは、結構自慢できます!
 )
)しかし、その中で機能性の高い、自由な設定が可能なソフトはこの奉行シリーズだけです!!
特に、勘定奉行(一般業種の会計用ソフト)と建設奉行(建設業専用の会計用ソフト)と商・蔵奉行(販売用と在庫管理用ソフト)がオススメです。
商蔵奉行は、自社商品や市場の細かなデータが出ます。
これを素にいろんな分析ができたり、傾向がわかるので、売上や利益を増やすための行動材料に利用できるところが一番のメリットだと思います。
※ただし、沢山の機能があるのでソレを上手に使いこなせないとダメですが・・・・。
多くの企業では、販売管理用のソフトがただの請求書発行用になっています。
このような、管理ソフトを経営に利用している会社は正直、ほとんど見たことがありません。
これは、とてももったいないことです。
楽天市場をはじめ、大手企業などは、顧客情報・商品情報のデータベースを利益を生む素として大いに利用しているからです。
自社の状況(傾向)を正確につかんでいくためには、データベースを利用するのが一番!!
なのに、ただの在庫管理用、請求書発行用だけに使っているのはもったいなーーーい!!!
営業会議や経営会議、部門会議などの会議資料としてこれらのデータベースを活用することは、利益改善に直結してきます!!
当社の顧問先でも、商奉行を導入されている企業があり、そこの会社では、このソフトで必要な項目を条件指定し、そのデータを集計した資料を使って半月に一度、経営会議をやりました。
その後、利益率が上がり、その期では大幅な利益改善ができました。
どうしてでしょうか?
それは、「見える化」をしたからです。
販売管理ソフトを使って経営資料を作成し、どこがどう悪いのか、良いのかをみんなで知ったからです。
そして、半月ごとにその状況をみんなで共有していくと、必然と意識が変わり、一人一人の行動が変わり、利益が改善され、それがまた数字となって見えることに自信が付き、また意識向上へと繋がっていったからです。
ただし、言っておきますけど・・・・。
これは、ずっと継続して内容を発展させていかないとマンネリ化してきます。
また、見える化してみんなの営業活動を検証するということを止めてしまうと、利益は下がるし、みんなの意識もいつしか下がってきます。
コレ、間違いなく!!
私個人的には、販売・在庫管理にはこの奉行シリーズを強く推しますね!
だって、ここまでいろんな条件指定していろんな集計表が出力できるソフトはないからです。
でも、定価がスタンドアロン版スーパーシステムで262,500円(Bシステムで210,000円)と結構高いですね。(商奉行・蔵奉行それぞれに上記金額となります)
※別途保守料金がそれぞれに必要になります。
いずれにしろ、これからは、どうやって利益を上げるか自分達で自社のデータから読み取り行動に繋げていかなければならないので、IT化は絶対に必要になってきます。
予算面もありますので、購入しやすくてそれなりに機能性も高いものをオススメします。
会計に関しては、弥生会計、ビズソフトのツカエル会計をオススメします。
販売・在庫管理は、弥生販売プロフェッショナルをオススメします。
給与は、給与革命を一押しします。
安いし、専用紙不要、保守料も安い、エクセル使用、年末調整までできて、これは当社の顧問先へもオススメしてます。
ただし、複雑なシフト体制のところには不向きです。
在庫を抱える業種では、在庫管理をせずして、利益改善はありえませんので、IT化を絶対にオススメしております!!
資金繰りにも大きく影響してきますからね!!!
顧客管理はどのように管理されていますか?
顧客区分をされていますか?
アナログ作業では、顧客の動向や営業販促活動のための資料をつくれませんので、これについてもIT化をされることをオススメします。
専用ソフトを購入される場合は、販促計画とその履歴管理ができるソフトを購入されることをオススメします。
単に、顧客情報だけを蓄積しても、顧客の動向は見えませんのでご注意ください。
なぜ、利益が上がらないか、資金繰りが大変なのか・・・。
その多くは、自社の現状をきちんと正確に捉えていないからです。
きちんと数値化されて、見える化されて、共有化されていないからです。
具体的行動を起こすためには、より詳細な情報が必要ですよね。
感覚的に行動しても成果はあがりませんよね。
顧客層(市場)の傾向や商品の動向の『真実』を経営者自信が、営業マン自信が自分の目で確認する必要があります!!
『真実』は数字です!
「数字は嘘をつかない!」を口癖となっておりますが、ホントにそうなんです。
数字→結果→真実
です。
そこには、誰の『情』も『感覚』も入っていません。
客観的な真実そのものです。
これを是非経営に活かしていただきたいんです。
それが、『自分で自分の会社を守る』ことだと思います。
当社は、『自力向上のお手伝い屋さん』でもあります。
自分の力で立って、歩くことが真の企業の力であり、それが地域活性化へ繋がると信じます。
一番大事な数字の部分を他人に作ってもらっていることは、この『真実』と距離があることになります。
外部委託していても、早く『真実』をつかめるようにする必要がありますね。
全ては、『自分で自分の会社を守るため』です。
IT化を進める場合、どこまで管理するかということを先に決めてから、諸所の設定をされることをオススメします。
※ちなにみ、会計のことを知らない事務機メーカー屋さんやコンピューター屋さんから購入される場合は、要注意です!!
初期設定が、将来の経営に活かせるような工夫をして設定されるわけではないので・・・・。
会計のプロだからできる、活用方法があります!!
企業の利益創出ができるかどうか大切な『自力』の部分です。
正しい有効な利用方法で活用されることをオススメします!!
OBC製品に限らず、導入支援や購入に関するアドバイスができますのでお気軽にご相談ください。
ご相談の方はコチラ→http://www.seijitsu-k.jp/inquiry/exec/
2010年04月12日
キャッシュフロー勉強会

こんばんは。
鏡でございますm(__)m
土曜日午前中は、経営者の為の決算書の見方勉強会の第二弾『キャッシュフロー』でした。
キャッシュフロー計算書の仕組みとその算出の仕方をお話しました。
資金繰り表とは違います。
1期分のキャッシュの流れを表したものです。
キャッシュの流れを3つに区分します。
①営業キャッシュフロー・・・・経常的な(通常の営業活動での)キャッシュの収支を表したもの
勿論、ここがプラスになっていないと大問題!!
資金調達(利益で調達する)の根本的な部分です。
自社の資金がどこから作られているか、感覚と事実にギャップはありませんか?
なぜ、頑張っても頑張っても楽にならないのか・・・。
根本的な問題(経営体質)が見えてきます。
②投資キャッシュフロー・・・・設備投資や機械や車両、建物、土地、有価証券などの取得と売却での
収支を表します。
通常、健全経営の会社では、将来の利益のために投資がなされるので
ここの部分の収支はマイナスになります。
プラスになるのは、営業キャッシュフローの資金不足を補うために
投資物件を売却して資金を調達した場合などです。
これは、一つの切り札になります。
根本的問題の解決にはならないので、あくまでも、一時的な対処です。
※①+②=フリーキャッシュフロー・・・この金額がプラスということは、本業で得た資金の範囲
内で投資が行われているということを表します。
マイナスの場合は、その逆で、本業での余剰資金を超えて
投資が行われていることになります。
→そのマイナス分はどうやって補充する?
借入金?貯金を取り崩す?
安易な投資は会社の安全性を揺るがす要因になるかも
しれません。
投資に充てられる資金は、できれば余剰資金から充てたい
ですよね。
その投資が無理していないか、よーく考えて支出したい
ものです。
③財務キャッシュフロー・・・・ここでの資金は、①や②の活動資金を支える資金になります。
つまり、借入金やその返済、社債の発行や償還、増資などです。
借入金がある会社は、通常はマイナスになりますよね。
返済していますから。
新規に借入をすると、そのときはプラスになるかもしれません。
が、その後は返済額がまたその分増額したりして、出が増えてきます。
利益を出していてもどうしても資金繰りに窮してしまう場合は、ここで
資金調達することに依存しているからかもしれません。
何故に、ここで調達しなければいけないのかをよく考えていただきたい
と思います。
いろんなケースがあります。
①+②+③=当期のキャッシュ増減額になります。
さて、前期末よりキャッシュが増えたか減ったのか、ではその要因がどこにあるのか・・・・。
キャッシュフロー計算書を作るとそれがよーーーくわかります。
決算を毎年何度も何度もやっていますが、自社のキャッシュフロー計算書は見られたことはありますか?
中小企業では義務ではないので、税理士さんもわざわざ自分の仕事を増やすことはしません。
でも、現代の経営はこのキャッシュが企業の生死を決定します。
自社のお金の流れを、その変化をリアルタイムに把握していかないと、どんなに営業や業務に没頭して頑張って受注し納品しても、『自社のキャッシュができる仕組み』を知っているのと、知らないのでは、先が見えない不安定な環境の中での舵取りの結果も大きく変わってきます。
なぜ、融資を申し込んでも断られたり減額されたりするのか。
納得いかない場合がありませんか?
銀行さんは、独自に企業のキャッシュフローを把握しているからです。
そこで、返済余力を見ているのです。
どの部分を見られているかわかりますか?
どうせ、経営するなら、銀行さんとも長く上手にお付き合いできるような経営をしたいですよね。
自社のどこに問題があるのかがわかってきます。
知ることは早ければ早いほど、行動に移した後からの結果が大きく変わってきます。
手遅れになってしまったらどうしようもありませんので・・・。
知らない
↓
判断材料(選択肢)が少ない
↓
選べない(相手の言いなり、交渉の余地なし)
↓
無駄や制限が発生(無駄なコストや行動の制限が発生)
↓
会社の燃費が悪くなる
↓
会社の体力が削がれていく
↓
資金難に陥り、何もできなくなる
↓
倒産
嫌なフローです

これからの経営者は、数字が読めないと大変な目に遭いますよ!!
だって、誰も真実を教えてくれないんですから!
全て自己責任。
自分で自分の会社を守らないと、誰も助けてはくれませんから!
数字が読めなくても大丈夫です。
とてもわかり易いと好評の勉強会をご用意しております!
少人数制ですので、周りに気兼ねなくご質問にもお答えできます!
経営者のための決算書の見方勉強会はコチラ→http://www.seijitsu-k.jp/pdf/seijitu02.pdf
5月以降も、第二第四土曜日の10:00~12:00で開催しております。
普通ではなかなか聞けない決算書の見方をお教えします。
きっと目から鱗間違いなし!!です。
どうしても日程が合わない方のために、出張勉強会を始めました。
会社内での、後継者や幹部の方を含めた勉強会に最適です!!
また、経営者の団体での勉強会にもオススメします。
勉強会料金:2時間30,000円(3名様まで、1名追加ごとに+3,000円の加算)
※開催日時は、お申し込み者様との協議の上で決定させていただきます。
開催場所は当社会議室(5名様程度まで可能)か、集中して開催できる場所をお申し込み者様での手配を
お願いします。
お申し込み、お問い合わせはコチラ→http://www.seijitsu-k.jp/inquiry/exec/
また、マンツーマンで受けたい方には日時を協議の上、当社会議室にて開催いたします。
勉強会料金:2時間12,000円
お申し込み、お問い合わせはコチラ→http://www.seijitsu-k.jp/inquiry/exec/
1社でも多く、数字がわかる経営者を増やそうと熱く熱く頑張っております!!!
お申し込みお待ちしておりますm(__)m