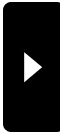2010年07月23日
『日々三省』
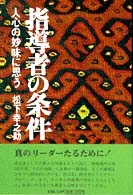
こんにちは。
鏡でございますm(__)m
↑↑↑ここ最近、寝る前に読んでいる本です。↑↑↑
その中で、『自問自答』というタイトルの文の中で、孔子の弟子である曾参(そうしん)という人の言葉からピックアップしました。
孔子よりも46歳も年下の弟子だそうです。
曾参の名は初めて知りました。
「私は、毎日3つのことについて、みずから反省している。第一は、人のために考え行動しながら、かえって忠実さを欠くことはなかったか、第二は、友人との交際で信義を欠くことはなかったか、第三には、学んでもいない、自分でもよくわかっていないことを人に教えたりはしなかったか、ということだ」
これは、曾参の有名なことばだそうです。
毎日の自分の行いについて自問自答をしているということ自体に指導者にとって非常に学ぶべきものがある。
指導者は自分の指導理念なり方策についてまちがいないか、あるいは自分の力をいうものを正しく把握しているかといったことについて、たえずみずからに問いみずから答えるということをくり返していかなければならない。そうした自問自答こそ、指導者が日々決して怠ってはならないことである。
自分一人で自問自答していたのでは十分わからないという場合もあるだろう。その時は、それを他の人にもたずねてみればいい。“自分はこう考えているが、どうだろうか”ということを謙虚にたずねてみる。
皆さんは、日々いくつの反省をなさっていますか?
曾参のように、“毎日必ずこのことを振り返ってみよう”というものありますか?
私は、決めていませんでした。
その都度、反省はしていますが、それだけではいけないですね。
「指導者のあり方というのはきわめて重要である。」
「指導者はあやまちなきを期すという上においては、きわめてきびしい自己検討を要求されているわけである。」と本書の中でもあります。
私の場合だったら、3つどころの反省では全然足らないですね(^_^;)
曾参のように、毎日反省すべきことを決めて毎日反省する、それを継続するというのはブレない自分であり続けるためには良いのではと思います。
これ↑やってみようと思います。
2010年07月15日
「どうしてお母さんは正面から話すの」

こんばんは。
鏡でございますm(__)m
本日のフードビジネス社員研修中の講師の茂田先生(ワークスタジオ花)のお話で、娘さんが反抗期に入り、親子でひどくやりあったときに娘さんが言われた言葉だそうです。
「どうしてお母さんはいつも正面から話すの。何で私の横にきて話さないの。」
この言葉を聞いて、先生はハッとされたそうです。
しかし、
「お母さんはどんなときでも一生あなたのお母さんだから、ずーっとやかましく言うよ。」
と返されたそうです。
でも、娘さんの言葉に反省されたのだそうです。
私も、このお話を聞いてハッとしました。
正面から話す⇒対面している⇒対立
横にきて話す⇒相手と同じ向きに座る、側に座る⇒相手の立場にたって話す
私もいつも子供たちには「正面から」話しています。
子供にとっては、母親がいつも「対立」している立場に感じているんでしょうか。
子供と話すとき、横に座って話すだけでも受け止める子供にとっては聞き入れ方が違ってくるのでしょうか。
先生の娘さんはいいところをつかれているなとちょっと感心もしてしまいました(^_^;)
コミュニケーションの研修の中でも、これに似た話を聞いたことあります。
対面に座ると相手と敵対してしまう。
ずらして斜めの位置に座れば良いとか、横はもっと親近感をいだけるとか・・・。
好きな人と座る場合は、横がいいかもしれませんね。
でも、まだそこまでの関係でない場合は、横だといきなりすぎるかもしれないので、ちょっと斜め向かいに座るのもいいかもしれません。
相手との関係で座る位置も変わってくるのはおもしろいです。
しかし、私も、ほんといつも子供たちのま正面からばかり言葉を発しているので、たまには横に座って子供の目線に立って話すこともしていかないといけないなと反省しました。
2010年07月13日
負けるが勝ち!!

こんばんは。
鏡でございますm(__)m
先日、当社の接遇マナー研修の先生のワークスタジオ花の茂田花子先生とお話していたら、「鏡さん、負けるが勝ちですよ」とおっしゃいました。
【目的を達成するためには、“負けて勝つ”んです。そのためには、いくらでも頭を下げますよ】
だそうです。
人のタイプの中には、常に“戦っている人”がいますね。
戦うとは、常に勝たなくてはならない人のことです。
どんなときでも、勝たなくちゃならないようです。
だから、絶対に自分から引きません。
負けたくないから。
そういう人を相手にするときは、まともに戦っても時間の無駄。
すぐさま“負けてあげる”のだそうです。
そして、こちらの目的を達成する。
相手もいい気分のまま。自分も目的を達成できる。
なるほど!
負けるが勝ちですね。
確かに!!
私もこの手を使っていこう!!
人間は感情の生き物ですものね。
そこを上手く利用して良好な人間関係を維持していく。そして、目的も達成する。
一石二鳥ですね!
2010年04月22日
『魅は与によって生じ求によって滅す』
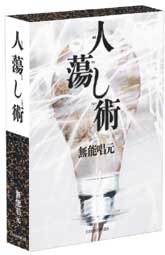
こんばんは。
鏡でございますm(__)m
今再読中の本より抜き出した言葉です。
無能唱元氏著『人蕩し術』(ひとたらしじゅつ)を毎日少しずつですが読んでおります。
『魅は与によって生じ求によって滅す』
とは、「あなたが他人に何か与えれば、あなたに“魅きつける力”は生じ、あなたが他人から何かを取ろうとすれば、その力は即座に消えてしまう」ということだそうです。
見た目の魅力や才能などの魅力といろいろと魅力と感じる要素はあります。
では、そのような容姿や才能などがないと、人は本当に魅力がないのでしょうか?
この本では、冒頭、そのことをはっきりと今日のタイトルの言葉で言い切ってます。
それらの要素はほんの一部分としての要素であり、その証拠に、お金持ちでも人気のない人がいるし、逆に何のとりえもなく風采の上がらない男性でも、奇妙に女性に人気のある人もいるからだと唱元氏は言ってます。では、誠実で人格の優れた人は魅力的なのか?これも、一部分であり、人間として立派であっても孤独な人は数多くいるとも言っています。(尊敬と魅力は別物であることを示している)
では、魅力とは一体何者なのか?
そして、どうすればそれを身につけられるのか?
その答えが、今日のタイトルの言葉
『魅は与によって生じ求によって滅す』です。
そうです。
魅力的な人になるためには、『与えればよい』のです。
なんか、拍子抜けするようですが・・・。
『与えればよい』という至極単純な答えでは・・・。
結構、真剣に「魅力的な人間になりたい」と思っていろいろと努力したりって・・・ありますよね・・・。
いろんな努力をしているのに・・・。
その中の一つ、ダイエットもそうですよね(^_^;)
それを、「与えればよい」だなんて・・・・。
このことを知ってか知らずか、「物を与える」天才ぶりを発揮したのは、皆さんもよくご存知の豊臣秀吉なんだそうです。
例えば、毛利との戦で、毛利方の高松城を水攻めにする際、途方もない土木工事を短期間に進めるために、百姓町人の欲を刺激して、土俵一俵運んでくれば銭百文と米一升を与えるという夢のような条件を出したそうです。
その結果、こんなおいしい話はないと発狂同然になって子供や老婆までも土俵をかつぎだし、たった12日で大堤防を完成させました。
また、戦で功のあった者に対する恩賞のやり方も、現代ビジネス社会でもあてはまると唱元氏は言っています。
恩賞に不公平があれば、不平不満で士気がゆるみ組織が乱れます。秀吉は恩賞はできるだけ戦が終わったその場で行うようにし、とくにめざましい戦功に対しては合戦の最中でさえ部下を走らせて、その場で行賞しました。
そして、多くの場合は金銀をつかんでその場で渡すため、戦場にはいつも金銀がいっぱい詰まった行李を運んだそうです。
これらのことからもわかるように、『物を与える』ということは、その人に魅力を発揮させる最も原型的なその例だそうです。
この「物」は、ときどき「お金」に変わったりします。
また、「形のないもの」(愛、笑顔、思いやりなど・・・)に変わったりもします。
さて、その『何らかのもの』を受け取る側にとっては、『5つの本能的衝動』のいずれかを充足してもらったために、与えてくれた相手に対し魅力を感じるのだそうです。
『5つの本能的衝動』とは、
①生存本能
②群居衝動
③自己重要感
④性欲
⑤好奇心
です。
中でも①の生存本能(「飢えへの恐怖」がその根底にはある)は、人間のみならず、あらゆる生命が生きていくための最も原初的、かつ最も強大な本能なのだそうです。
ということは逆を考えると・・・、つまり①の生存本能を脅かされるようなことがあれば、それは魅力がなくなるどころか、相手との距離を大きく遠ざけるものになってしまうということになりますね。
繰り返しになりますが、魅力が生ずるか否かは、正に他人に対し、5つの本能的衝動の内いずれかを充足させるものを「与えたかどうか」にかかってくるということですね。
与え続けることはある意味大変でもありますが・・・。
さてさて、長くなりましたが、いかがでしょうか?
何かを与えていますか?
求すれば滅するわけです。
例えば、リストラなんかが一番わかり易いですよね。
従業員の給与を一部カットしたりして、コスト削減を図りますよね。社長は会社のために苦渋の決断を持って臨んだのかもしれませんが、①の生存本能にモロに刺激がいってしまいますよね。
①の生存本能の根底は『飢えへの恐怖』です。
つまり、食っていけるか(生活できるか)という漠然とした不安を一層かりたてることをやっていることになりますよね。→魅力が即座に滅するわけです→士気が下がる→社員がまとまらない→組織としての成果があがらない→経営が更に悪化する
と負のスパイラルに入ってしまうかもしれません(>_<)
人をまとめていく立場にあるもの、経営者、経営幹部の方は、何らかのものを常に与え続けていく必要がありそうです。
与えないで、求めてばかりいてもいけないですね。
また、営業でもコレってあてはまるのかなと思います。
お客様にまず「与える」。
これを、お客様から「契約」をいただこう(求めよう)とすると、即座に滅するわけですね(>_<)
何かを組織的に成し遂げたり、相手を動かすためなどにもこの『魅は与によって生じ求によって滅す』があてはまるのでは・・・と思います。
まだ、この本の1/4程度しか読み終わってませんが、また良い言葉がありましたらご紹介します。
2010年01月23日
『三宝』

こんにちは、鏡でございますm(__)m
本日は、また加島祥造著の「ほっとする老子のことば」より
『三宝』
(老子道徳経第六十七章)
私は
三つの宝を持っていて、それをとても
大切にしている。
その一は愛すること、
その二は倹約すること、
その三は世の人の先に立たぬこと。
「愛すること」は孤独への恐れを癒す最上の方法であること。
「倹約すること」とは、「欲張るな」ということ。欲張らなければ人は平穏な気持ちでいられること。
「人の先に立たず」とは、競争せずに自分のペースで生きよということ。そうすれば、人に追い込まれても恐れないでいられる。
この三つの言葉は日常生活の上で生じる不安を軽減してくれ、私達を励まし、生きる勇気を与えてくれる。
と、加島氏は言っています。
この言葉、宝なんですね。
愛すること、
倹約すること、
世の人の先に立たぬこと。
シンプルな言葉ですが、ものすごく説得力があります。
ものすごく心打たれてしまいます。(打たれてしまいました!)
自分の『三宝』にしたいですね。
この本を読むのは二度目です。
本のタイトルのように、
ほっとしますね(*^_^*)